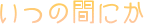お題
□いつの間にか
1ページ/1ページ
思えば、幼い時分私は、必要とされていないのだとばかり思って過ごしていた。
医家の嫡男として生まれながらも、既に家は義兄のもので。
体も弱くいつ死ぬか分からないから・と、ずっと部屋住み扱いで。
息苦しい家から開放され、養子に行った事もあったが…養父はろくに記憶にも残らない程早くに逝ってしまった。
それだから私は、結局実家に戻り養育される事になったのだった。
別に母や姉や義兄たちが嫌いだった訳では無いが、やはり私は異端だったのだ。
どうしたいのかも、どうしたら良いのかも分からず、闇雲に藻掻いていた…そんな私を救ってくれたのが、高杉だった。
近所で赤子が産まれたと聞いて、祝いに駆け付けたのが奴との出会い。
その実、私は余り乗り気では無かった。
ただ、抱いてみてやってくれと言われて、そう言われたのに無下に断るのは印象が悪いだろうと思い従っただけだった。
産まれて間もない赤子はまるで猿のような顔をしていて、これが本当に人間なのかなどと不謹慎な事ばかりを考えていた。
しかし、返そうとしたその時。
奴は私の顔を見て、実に嬉しそうに、にこりと笑ったのだ。
ふと涙が出そうになり、私は母の腕に抱かれる奴の手に、そっと触れてみた。
すると、その幼いちいさなちいさな手は、放したく無いとばかりにきゅっと私の指を握り締めてくる。
そう…必要とされているという感覚を、惜しまれているのだという感覚を、彼は私に初めて与えてくれたのだった。
----------------------------------
「本当に、それが嬉しくてね。この手がある限り、私は頑張れると思ったものだよ」
長々しい回想を終え漸く現在に帰ってきた桂は、溜め息混じりに呟いた。
感嘆の物ではなく、呆れから来るものなのだろう…眉間には小さく皺が寄っている。
「へェ…それで?」
「今ではその同じ手が、私を押し倒して衿を寛げていると思うと…何だかな」
「万感の思いってヤツですか」
「ふざけるな、全くもって違うぞ。そうだなあ、世の無常と云うか非情と云うか…」
悲劇を演じる役者のように、とうとうと非難の言葉を並べる桂は、それでも高杉の袖をぎゅっと握って放さない侭である。
今では立場が逆転してしまっているではないかと、高杉はくつくつ笑った。
「何を言ってるんだか…正直な所、厭では無いくせに」
椰喩すれば、下敷きになっている男は更に頬を赤らめて、金魚のように口をぱくぱくして必死に否定の言を捜しだす。
高杉はその開いた唇に、好都合だとばかりに吸い付いた。
先程桂が食べていた羊羹の味がほんのりと広がる、甘い甘い接吻。
仕掛け人が気の済むまで散々愉しんだ後、漸く二人の唇は離れる。
荒く息を吐く長年の思い人の姿に、高杉は満足気に柔らかに微笑んだ。
「桂さんは、可愛い人だな」
桂は、そんな元弟分・現恋人未満の様子に、ちょっと不機嫌そうに…しかし何処か嬉しそうに小さく呟いた。
「本当に、ふざけるな…晋作」
「折角のこの機会にふざけないで、どうしろと言うんですかね、あんたは」
そう言いながら高杉は蝋燭の芯を消し、その侭桂の腰を抱き寄せた。
まだまだ宵の口だが、それでもゆうるりと闇が空間を満たしてゆく。
じきに、夜の帳が訪れるだろう。
本当はそれまでは待っていて欲しかったのだけれど・と。
ぼそりと呟かれた桂の本音を、既に行為に夢中になっていた高杉は見事聞き逃したのであった。
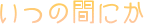
.